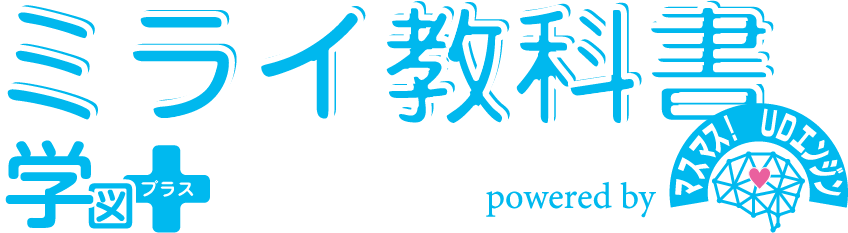gkt-horizontal-line
<1年p.90>
2章 「文字式」を学んで
できるようになったこと 身のまわりの課題へ ▷P.[mathjax] \(93\),[mathjax] \(94\),[mathjax] \(286\)
文字を使って数量の関係や求めた結果を表したり,文字を使って表された数量の関係を読み取ったりすることができる。
1次式の計算ができる。
身のまわりや数学の中から見つけた問題を考えるとき,文字式を解決に利用することができる。
さらに学んでみたいこと
これからもっと学んでみたいことや,疑問に思ったことを書いておこう。
gkt-horizontal-line
数学へのいざない 和算における文字を使った式
江戸時代, 日本には 「和算」 という日本独自の数学がありました。鎖国中の日本は,ヨーロッパ諸国と切り離された状況の中,独自の発展をし,世界でも最高レベルの数学を行っていました。その和算を発展させた和算家に, 関孝和(1640頃〜1708)がいます。ニュートンやライプニッツとほぼ同時期に活躍した人です。
関孝和は,和算が独自の発展をするにあたって,重要な役割を果たしました。1674年に『発微算法』を著し,傍書法と呼ばれる記号法を発明して,和算が高等数学として発展するための基礎をつくりました。
傍書法とは,文字を使って式を表す方法のことです。現在では,数字はアラビア数字,文字は英文字を使って表していますが,傍書法では,数字は算木,文字は甲,乙,丙などの文字を使って表していました。このことにより,式を簡単に表すことができるようになり,筆算で計算できるようになりました。
彼は,ほかにもさまざまな業績を残しています。関孝和について,いろいろ調べてみましょう。
関連 P.292